2024年版 農地相続のメリット・デメリット 手続きと税金を解説
- 最短10日
即現金化! - 圧倒的な高額
買取に自信! - 売却・土地活
用の相談無料
お気軽にご連絡ください
まずはお気軽に無料
相談をご利用下さい
ライズでは買取用地の情報を求めております。法人個人問わず幅広く情報をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
下記の資料があると査定がスムーズになります!
3つの資料
①土地の謄本 ②土地の公図 ③航空写真
※道と接している土地しか買取できません
※原則200坪(600平米)以上の用地が対象です。
受付 平日 9:00 〜 18:00
農地相続のポイント 知っておくべき法律と手続き

農地相続は、一般的な不動産相続と比べて独自の法律や手続きが関わるため、注意が必要です。農地を次世代に引き継ぐためには、農地法や相続税法などの基本的な法律を理解し、適切な手続きを行うことが重要です。本コラムでは、農地相続の際に知っておくべき法律や手続きについて詳しく解説し、スムーズな相続を実現するためのポイントをご紹介します。
農地を相続するメリット・デメリット

農地を相続するメリットとデメリットを考慮し、農地相続の決定を行うことが重要です。農地を有効に活用するためには、専門家のアドバイスを受けることも検討する価値があります。
農地を相続するメリット
-
1. 土地の資産価値
農地は不動産としての資産価値があり、将来的な土地の価値上昇が期待できることがあります。
-
2. 農業の継続
家族経営の農業を続けることで、地域社会への貢献や伝統を守ることができます。
-
3. 収益源
農地を利用して農作物を生産し、収益を得ることができます。特に、直売所や観光農園などの新しい事業展開も可能です。
-
4. 税制優遇
農地を相続する際には、一定の条件を満たすことで相続税の納税猶予や軽減措置が適用されることがあります。
-
5. 多目的利用
農地を農業以外の目的(例えば、再生可能エネルギー施設の設置など)に利用することで、新たな収益源を得る可能性があります。
農地を相続するデメリット
-
1. 維持管理の負担
農地の維持管理には手間と費用がかかります。相続人が農業に従事しない場合、放棄地となるリスクがあります。
-
2. 固定資産税の負担
農地を保有することで、固定資産税の支払いが必要となります。特に利用しない土地の場合、この負担が大きく感じられます。
-
3. 農業経営の難しさ
農業には専門知識と経験が必要です。相続人がこれらを持たない場合、農業経営が困難になる可能性があります。
-
4. 相続税の負担
相続税の負担が大きい場合、他の財産と合わせて相続税の納税が困難になることがあります。
-
5. 土地の流動性の低さ
農地の売却や転用には制約が多く、自由に土地を処分することが難しい場合があります。
農地を放棄する場合のデメリット

農地を放棄する場合には、以下のようなデメリットを考慮し、農地を放棄する際には慎重な判断が求められます。放棄せずに有効活用する方法を検討することが望ましいでしょう。
-
税負担の増加
放棄された農地は雑種地として扱われることが多く、固定資産税が高くなる可能性があります。これにより、税負担が増加します。
-
土地の価値低下
管理されない土地は荒れ果て、雑草や灌木が生い茂ることで土地の価値が下がります。売却や活用が難しくなります。
-
周辺環境への悪影響
放棄地は野生動物や害虫の温床となり、周辺の農地や住居に悪影響を及ぼすことがあります。これにより、近隣住民とのトラブルが発生する可能性もあります。
-
自然災害リスクの増大
手入れされていない土地は水はけが悪くなり、豪雨時の水害や土砂崩れのリスクが高まります。これにより、周辺地域の安全が脅かされることがあります。
-
行政からの指導や命令
長期間放置された農地については、自治体から管理改善の指導や命令が出されることがあります。これにより、思わぬ負担や義務が生じる可能性があります。
-
景観の悪化
放棄された農地は地域の景観を損ない、観光資源や住環境にマイナスの影響を与えます。これにより、地域全体の魅力が低下することがあります。
-
再利用や転用の困難さ
放棄された土地を再利用や転用する際には、再度整備するための費用や労力が必要となります。これにより、再活用のハードルが高くなります。
-
法的な問題
農地を放棄することにより、農地法に基づく法的な問題が生じることがあります。これにより、相続や売買の際にトラブルが発生する可能性があります。
農地の相続手続き・必要書類

農地の相続には、一般的な不動産相続とは異なる特別な手続きが必要です。以下は、農地相続における主な手続きと必要書類についての解説です。
-
1. 相続人の確定と遺産分割協議
相続人全員の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続関係を示す書類(遺言書や遺産分割協議書)を準備します。
-
2. 法務局での相続登記
農地の名義を相続人に変更するため、以下の書類を法務局に提出します。
相続登記申請書
被相続人の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
被相続人の住民票除票
固定資産評価証明書
登記事項証明書
遺産分割協議書または遺言書 -
3. 農業委員会への届出
農地を相続したことを知った日から10ヶ月以内に、農業委員会に届出を行う必要があります。届出には以下の書類が必要です。
農地相続登記後の登記事項証明書
農地の固定資産評価証明書
農業委員会が指定する届出書
農地相続をしない場合の対応方法

農地の相続には、一般的な不動産相続とは異なる特別な手続きが必要です。以下は、農地相続における主な手続きと必要書類についての解説です。
-
1. 相続放棄
相続放棄をすることで、農地を含むすべての遺産について相続の権利を放棄することができます。相続放棄を行うには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。この手続きは、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行う必要があります。必要書類としては、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票、相続放棄する人の戸籍謄本などがあります。
-
2. 農地の売却
相続人全員が同意した場合、農地を売却することも可能です。農地を売却する際には、農地法に基づく手続きが必要となります。市街化区域にある農地の場合は農業委員会への届出が必要で、その他の区域にある農地の場合は都道府県知事の許可が必要です。
-
3. 農地の賃貸
農地を賃貸することで、自ら農業を行わなくても農地の維持管理を行うことができます。賃貸借契約を結ぶには、農業委員会の許可が必要です。この方法は、農地を荒らさずに管理する手段として有効です。
-
4. 遺産分割協議による換価分割
遺産分割協議において、農地を現金化して分配する換価分割も検討できます。この場合、相続人全員が協力して農地を売却し、売却代金を分配します。売却には農地法の手続きを踏む必要があり、許可や届出が必要です。
-
5. 農業委員会への届出
農地の相続放棄や売却が行われない場合でも、農業委員会への届出は必要です。相続が発生してから10ヶ月以内に農業委員会へ届出を行わなければならず、これを怠ると過料が課されることがあります。
農地を含む土地の
相続登記義務化

2024年4月1日から、日本では土地や不動産の相続登記が義務化されます。相続人は土地を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、これを怠ると10万円以下の罰金が科せられます。また、義務化前に相続された未登記の農地も対象となります。農地の相続に伴うトラブルや法的問題を未然に防ぐためにも農地を持っている、親が農業をしている人などは適切な対処が必要となります。
青地・1種農地は
農業以外の使用不可

日本の農地法では、農地の種類に応じて利用できる用途が厳しく制限されています。特に「青地」と「1種農地」は、その利用に関して最も厳しい制限が設けられているカテゴリーです。これらの農地は、主に農業専用地域に指定されており、農業以外の用途に転用することが困難です。 「青地」とは、農業振興地域内の特に保護すべき優良農地を指し、農地としての価値が非常に高いことから、農業以外の目的での利用が法律で制限されています。同様に、「1種農地」も農業生産緑地地域内に位置する農地で、こちらも農業の継続が求められ、宅地化など他の用途への転用は原則禁止されています。 これらの農地を農業以外の目的で使用するには、地方自治体の許可が必要であり、転用許可を得るためには非常に厳しい基準を満たす必要があります。例えば、農地を工業用地や住宅地として開発する場合、地域社会に与える影響や農地保全の観点から評価され、多くの場合、許可が下りにくいのが現状です。 このように青地や1種農地の厳格な利用制限は日本の貴重な農業資源を守るための措置として重要な役割を果たしていますが、農地所有者にとっては利用の選択肢が限られるというデメリットも伴います。
日本の法律では農地を
手放すのにお金がかかる
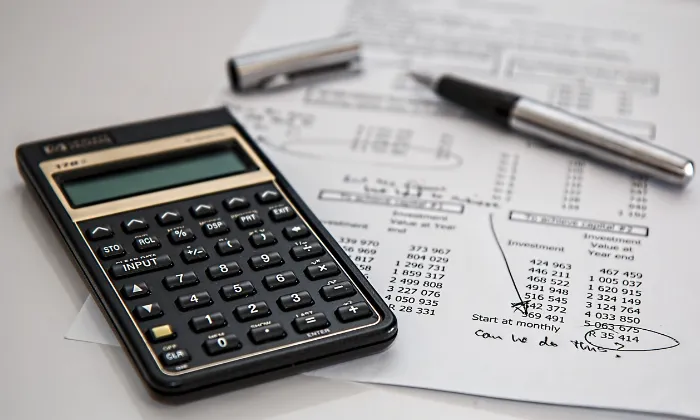
日本において農地を手放す際、多くのケースで様々な費用が発生することがあります。この費用は、単に土地を売却する行為自体のコストだけでなく、法的手続きや税金の面からも考慮する必要があります。 まず、農地の売却には通常、不動産仲介手数料がかかります。これは売却額の数パーセントを仲介業者に支払う形で発生し、土地の価格や契約条件によって変動します。また、売買契約を結ぶ際には印紙税が必要となり、これも売買価格に応じてコストが増加します。 さらに、農地の場合、特に税金面で注意が必要です。農地を売却すると、土地の譲渡所得に対して所得税が課されます。特に長期保有の農地の場合、大きなキャピタルゲインが発生することもあり、その税金が重くのしかかることがあります。また、相続や贈与によって農地を手放す場合でも、相続税や贈与税の対象となるため、税務上の準備と対策が必要です。 さらに、農地転用の際には転用許可申請が必要となる場合があり、これには申請料や関連する手数料が発生します。農地を非農業用途に転用する場合には、農地法に基づく厳しい規制があり、適切な手続きを経なければならないため、手続きの複雑さとそれに伴うコストが増大する傾向にあります。
まずはお気軽に無料
相談をご利用下さい
ライズでは買取用地の情報を求めております。法人個人問わず幅広く情報をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
下記の資料があると査定がスムーズになります!
3つの資料
①土地の謄本 ②土地の公図 ③航空写真
※道と接している土地しか買取できません
※原則200坪(600平米)以上の用地が対象です。
受付 平日 9:00 〜 18:00
農地売却の流れとは
-
相談と見積もり

最初に、農地の所有者が農地買取を行う企業や機関に連絡を取り、相談を行います。この段階で、農地の位置、面積、現在の使用状況などの基本情報が共有されます。
-
現地調査

買取を検討する企業が農地の現地調査を実施し、土地の実際の状態を確認します。この調査には、土壌の質、アクセスの良さ、周囲の環境などが含まれます。
-
詳細な見積もりと条件の提示

現地調査の結果を踏まえ、最終的な買取価格や条件が提示されます。この時点で、買取条件に関する交渉が行われることもあります。
-
契約の締結

両者の合意に基づいて正式な買取契約が締結されます。契約には、価格、支払い条件、土地の引き渡し時期などが明記されます。
農地売却の税金

農地を売却する際には、売却益に対して税金が課税されます。ここでは、農地売却に関連する主な税金について説明します。農地売却における税金は、個々の売却事情や土地の特性、さらには地域による規定の違いなどによって複雑になることがあります。したがって、農地を売却する際には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
-
所得税
農地の売却によって得られた利益(譲渡所得)に対して所得税がかかります。譲渡所得は、売却価格から取得費や売却にかかる費用を差し引いた額です。所得税の税率は、その所得の総額に応じた累進課税が適用されますが、農地の場合、特定の条件を満たすと特別な税率が適用されることがあります。
-
住民税
所得税とは別に住民税が課されます。住民税の税率は、一律10%(内訳:都道府県民税4%、市町村民税6%)です。また、特定の条件を満たす場合、特別控除や軽減措置が適用されることもありますので、詳細は自治体の窓口や税理士に相談することをおすすめします。
-
固定資産税・都市計画税
売却によって農地の所有権が移転するため、その時点で売主の固定資産税の納税義務は終了します。ただし、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課されるため、その年度分の税金は売主が支払うことが一般的です。売却後の固定資産税の負担については、買主との間で協議して清算する場合もあります。固定資産税の額は、土地の評価額に基づいて計算されるため、具体的な金額は自治体の評価額通知書を確認する必要があります。
-
印紙税
印紙税は契約書の記載金額に応じて決まり、契約金額が500万円を超え1000万円以下の場合は1万円、1000万円を超え5000万円以下の場合は2万円など、段階的に税額が設定されています。この印紙税は売買契約書に印紙を貼付して納税する形式です。契約書に印紙が貼付されていない場合や金額が不足している場合には、過怠税が課されることがありますので、注意が必要です。詳細は国税庁のウェブサイトで確認できます。
-
譲渡所得の特例
農地を売却する際の譲渡所得には特例が適用されることがあります。特に、「収用等に伴う特別控除」や「特定の居住用財産の買換え特例」などがあります。例えば、農地が公共事業のために収用される場合、5000万円の特別控除が受けられます。また、一定の要件を満たす場合、譲渡益に対して課税される所得税・住民税が軽減される特例もあります。これらの特例を適用するには、事前に税務署や専門家に相談し、必要な手続きを行うことが重要です。詳細は国税庁のウェブサイトで確認できます。
農地の売却方法
農地の基本区分を知る

日本の法制度は、これらの農地を通じて農業の持続可能性と国土の戦略的な利用を図っており、農地の適切な管理と利用が求められています。これらの区分は、農地の保護と適切な利用を確保するために設けられており、各種の農地での活動や開発はこれらの法的枠組みのもとで行われます。特に第1種農地は、その農業的価値が高いため、農業以外の目的での利用には厳しい制限が課されています。各地域の計画や発展の背景に応じて、これらの分類は適切な土地利用を促進する重要な役割を果たしています。
-
農用地区域内農地
農用地区域内農地は、都市計画法に基づいて特定された農業専用区域内の土地を指します。これは、農業の促進と土地の有効活用を図るため、農業が主な用途とされる地域に設定されています。この区域内の農地は、農業生産基盤の保全が強く意識され、農地としての利用価値を維持するための制約が多く設けられています。たとえば、非農業目的での土地利用が原則として許可されていません。
-
甲種農地
甲種農地は、農業生産性が高い優良農地を指します。特に、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が指定します。農地の転用や売却には厳しい規制があり、農地法に基づく許可が必要です。このため、農地の保全と農業生産の維持が重視されます。甲種農地は、通常、農地としての利用が求められ、非農業用途への転用は認められにくいです。
-
第1種農地
特に農業生産性が高く、かつ都市化の影響を受けにくい地域の農地を指します。この区分の農地は、優良な農業地として保全されることが求められ、農地法に基づく厳しい規制があります。非農業用途への転用は基本的に認められず、農業専用地域として保護されています。このため、農地転用の許可を得るのは非常に難しいです。
-
第2種農地
農業生産に適しているものの、将来的に市街地化が見込まれる地域の農地を指します。この区分の農地は、農業用途の維持が推奨されますが、都市計画や開発の進展に伴い、転用が比較的容易に認められる場合があります。第1種農地ほど厳しい規制はなく、都市化の圧力に対応して農地転用が許可されることが多いです。第2種農地の扱いは、地域の都市計画と農業のバランスを考慮して決定されます。
-
第3種農地
第3種農地は、農業生産性が低く、すでに市街地化が進んでいるか、今後市街地化が強く見込まれる地域の農地を指します。この区分の農地は、他の用途への転用が比較的容易に認められることが多いです。市街化調整区域に含まれ、工場、住宅地、商業地などへの転用が進むことがあります。第3種農地の扱いは、地域の都市計画や開発計画に沿って決定されるため、具体的な転用条件は自治体によって異なります。
農地転用して売却する

農地を転用して売却する場合、農地法に基づく転用許可が必要となります。これは、農地を他の用途(例えば住宅地や商業施設など)に変更することを目的としています。転用許可を得るためには、市町村の農業委員会への申請が必要で、地域の農業の維持や土地利用の計画に基づいて許可が下りるかが決定されます。転用が認められると、農地はより広範な市場で売却が可能になり、価格も非農地としての評価がされるため、高価で売却できる可能性が高くなります。
転用許可を得る過程では、地域の実情に合わせた計画書の提出が求められることが一般的です。計画書には転用後の用途、地域社会への影響、環境保全措置などが含まれます。この手続きは時間がかかる場合が多く、また転用後の用途が公益性を損なうと判断される場合には許可が下りないこともあります。
農地転用せず売却する

農地を農地のまま売却する場合、主に農業従事者や農地所有適格法人への売却が一般的です。この方法は、転用許可の申請が不要で、比較的スムーズに進めることが可能です。ただし、農地の売却価格は転用した土地に比べて低い傾向にありますが、速やかに手続きを進めることができるため、早期に資金化を図ることができます。 農地のまま売却する際には、農地法第3条に基づく売買契約の届出が必要です。この届出は、農地を購入する者が農業を営む意思と能力があることを示すもので、市町村の農業委員会に提出されます。売却できる対象者は限られているため、購入希望者が見つかりにくい場合もありますが、地域の農業を守ることに貢献する方法と言えます。
まずはお気軽に無料
相談をご利用下さい
ライズでは買取用地の情報を求めております。法人個人問わず幅広く情報をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
下記の資料があると査定がスムーズになります!
3つの資料
①土地の謄本 ②土地の公図 ③航空写真
※道と接している土地しか買取できません
※原則200坪(600平米)以上の用地が対象です。
受付 平日 9:00 〜 18:00
農地の売買に必要な書類

農地の売却には下記の書類が必要です。書類によっては取得に時間を要する場合もありますので、早めに準備を進める事で手続きを円滑に進めることが可能となります。
-
1. 農地売買契約書
内容: 売買の条件や価格、引渡し時期などを明記します。
備考: 双方の署名捺印が必要です。 -
2. 農地法第3条の許可書または届出書
内容: 農地転用が伴わない売買の場合、農地法第3条に基づく許可を受ける必要があります。
備考: 農業委員会への申請が必要です。 -
3. 土地登記簿謄本
内容: 登記情報を確認するための書類です。
備考: 法務局で取得します。 -
4. 公図(地籍図)
内容: 農地の位置や境界を示す地図です。
備考: 市区町村の役所や法務局で取得します。 -
5. 固定資産評価証明書
内容: 農地の評価額を証明する書類です。
備考: 市区町村の役所で取得します。 -
6. 身分証明書
内容: 売主および買主の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)。
備考: 売買契約の際に必要です。 -
7. 印鑑証明書
内容: 売主および買主の実印の証明書です。
備考: 市区町村の役所で取得します。 -
8. 委任状(必要な場合)
内容: 代理人に手続きを委任する場合に必要です。
備考: 売主または買主が手続きを代理人に委任する場合に準備します。 -
9. その他の書類
測量図: 境界確定のために必要な場合があります。
建物の有無証明書: 農地上に建物がある場合、その確認のために必要です。
農地の売却相場

日本の法制度は、これらの農地を通じて農業の持続可能性と国土の戦略的な利用を図っており、農地の適切な管理と利用が求められています。これらの区分は、農地の保護と適切な利用を確保するために設けられており、各種の農地での活動や開発はこれらの法的枠組みのもとで行われます。特に第1種農地は、その農業的価値が高いため、農業以外の目的での利用には厳しい制限が課されています。各地域の計画や発展の背景に応じて、これらの分類は適切な土地利用を促進する重要な役割を果たしています。
-
地理的な位置
地域によって農地の価格は大きく異なります。一般的に都市部に近いほど、または交通の便が良い場所では価格が高くなる傾向にあります。
-
用途制限の有無
農地の中には、建築制限があるために利用の幅が限られるものがあります。これらの制限が厳しい地域では、相場が低く抑えられることが一般的です。
-
地形や土壌の状態
平坦で耕作しやすい土地や、肥沃な土壌を持つ農地は高価格で取引されることが多いです。
-
農地のサイズ
大きな一括の農地は、小さな分割された農地よりも高価で売れることがあります。
-
市場の需要と供給
農産物の市場価格や農業政策の変化により、農地への需要が増減し、これが直接的に地価に反映されます。
農地の売却が難しい理由

農地の売却が難しい理由には、以下のような複数の要因があります。
-
1. 法的規制
農地は「農地法」によって厳しく規制されています。農地を他の用途に転用する場合、農地法第4条および第5条の許可が必要です。この許可を得るためには、厳しい条件を満たさなければならず、手続きが煩雑で時間がかかることがあります。
-
2. 農業委員会の承認
農地の売却には、地域の農業委員会の承認が必要です。農業委員会は農地の適正利用を監視する役割を担っており、農業振興地域内の農地の売却には特に厳しい審査が行われます。農業従事者以外への売却は認められにくいです。
-
3. 転用の難しさ
農地を農地以外の用途(住宅地や商業地など)に転用するには、都市計画法や市街化調整区域の規制も関与します。特に市街化調整区域に指定されている農地の転用は非常に難しく、行政の許可がほとんど下りないことが多いです。
-
4. 市場需要の限定
農地の需要は、都市部の土地と比べて限定的です。特に農業従事者が少なくなっている地域では、農地の買い手を見つけることが難しくなります。加えて、農業従事者が購入する際にも、既に十分な農地を保有している場合や、新たな農地を必要としない場合が多いです。
-
5. 経済的要因
農地の評価額は市場価値よりも低く見積もられることが多いです。特に過疎地や農業経営が厳しい地域では、農地の売却価格が期待よりも低くなる傾向があります。このため、売却するインセンティブが減少し、売却が難しくなります。
-
6. 手続きの煩雑さ
農地の売却には、多くの書類や手続きが必要です。例えば、売買契約書、農地法の許可書、公図、登記簿謄本、固定資産評価証明書などが必要で、これらを全て準備するのに多くの時間と労力がかかります
使わない農地は
売却すべき?

使わない農地を売却した方が良い理由には、以下のような要因が挙げられます。
-
1. 維持管理コストの削減
使わない農地であっても、固定資産税や管理費用がかかります。雑草の除去やフェンスの修理、害虫対策などのメンテナンスは定期的に行わなければなりません。これらの費用は使わない農地を所有し続けることで積み重なり、経済的な負担となります。
-
2. 土地の有効活用
農地を売却することで、他の農業従事者や新規就農者がその土地を有効に活用できる可能性があります。これにより、地域の農業生産性が向上し、食料供給の安定にも寄与します。また、農地が適切に管理されることで、地域の景観維持や環境保全にも貢献できます。
-
3. 資金の有効活用
農地を売却して得られる資金を他の投資や事業に活用することができます。例えば、新しいビジネスの立ち上げや不動産投資、教育資金や老後資金として利用することができます。これにより、資産の流動性が高まり、経済的な安定を図ることができます。
-
4. 相続問題の回避
農地を相続する際には、その評価額に基づいた相続税が課されます。農地を相続する場合、相続人が農業に従事しない場合や、相続人が複数いる場合には土地の分割や管理が難しくなることがあります。売却することで、相続時のトラブルを回避し、資産を現金化して公平に分配することが可能になります。
-
5. 地域経済への貢献
農地の売却によって新たな所有者が農業を続けることで、地域の経済活動が活発になります。農地が放置されることで周辺地域の地価が下がるリスクを回避し、地域の経済発展に寄与することができます。
農地売却のよくある質問
-
Q登記費用はどうなりますか
登記費用等は全て弊社負担いたします。
ご名義者がお亡くなりになっていますと、まず相続者が登記してからの契約となります。 -
Q契約した後の管理はどうなりますか
所有権移転登記が終わるまでは管理をお願いしています。
-
Q太陽光を立てることで隣の農地に影ができるなど周囲に迷惑をかけることはありませんか。
原則真下に影ができるようにパネルを設置するため、近隣の農地に影ができて迷惑がかかることはございません。
-
Q農業委員会を通して正規の運営でしょうか
各市町村の農業委員会に営農計画書を提出し認められた場合のみのご契約ですのでご安心ください。

